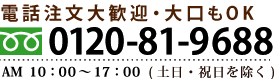お米の値段はホントに高いですか?
お茶碗一杯の価格52円は、お米5kgを4000円としてお茶碗一杯のお米(65g)で、計算しています。

精米はお米の温度を高温にしないことがおコメを劣化させない
「お米」は本当に高いのでしょうか。安心して主食をあたり前にいただけるように考えてみましょう。作る人と食べる人がお互いに「食」という意識で分かち合う価値を共有できないでしょうか。
おコメ作りする人が急速に減っていく
日本のおコメ生産者人口は、長期的に減少傾向が続いています。1955年には農家人口が約3,635万人でしたが、その後一貫して減少し、2020年には約349万人までに、65年間で90%落ち込みました。また、総農家数も1955年の約604万戸から2020年には約175万戸へと、65年間前の29%に減少しています。
特に水稲(おコメ)農家に限ると、1970年には約466万戸あったものが、2020年には約70万戸と、50年間で7割減少しています。このように、おコメ生産者人口は急速に減少しており、同時に高齢化も進行しています。
この背景には、農業従事者の高齢化や後継者不足、農業の収益性の低下などがあり、その根底にはお米価格の低迷と生産者の生産意欲の減少や将来不安があげられます。このような状況から今後も減少傾向が続くと見込まれています。
お米高騰の背景を考える
おコメの値段が高騰している背景には、複数の要因が重なっています。主な理由としておコメの値段が高いのは、異常気象による収穫量減少と品質低下、需要の増加、生産コストの上昇、政策による主食用米の生産減少、業者間の投機的取引など、複数の要因が重なっているためです。今後もこれらの要因が続く限り、米価の高止まりが予想されています。

庄内平野は鳥海山や月山の膨大な雪を水源に潤う
1,異常気象・猛暑による収穫量の減少
近年の地球温暖化や異常気象の影響で、日本各地で猛暑が続いています。高温は米の生育や登熟(実が成熟する過程)に悪影響を及ぼし、品質低下や収穫量の減少を招いています。これが供給不足を引き起こし、価格上昇の大きな要因となっています。
2,需要の増加
コロナ禍明けのインバウンド(訪日外国人観光客)の増加や、健康志向の高まりによる家庭での米消費の増加など、需要が拡大しています。外食産業やホテル業界での米需要も一気に回復し、全体的な消費量が増えたことも価格を押し上げています。
3,生産コストの上昇
農業用機械の燃料費や肥料代、人件費など、米の生産にかかるコストも上昇しています。これが農家の負担となり、価格に転嫁される形で消費者が支払う米価も上がっています。
4,減反政策や飼料用米の影響
2018年まで、政府やJA農協による減反政策(生産調整)や、農家が主食用米から補助金の手厚い飼料用米への作付け転換を進めたことにより、主食用米の生産量が減少しています。また、根も政策により、将来への不安も重なり生産者側では生産意欲が減退してしまいました。これも供給不足を招き、価格高騰の一因となっています。
5,業者間の取引や投機的な動き
卸売業者間でのスポット取引が増え、投機的な動きも見られます。安い時に仕入れて高く売る業者が増えたことで、流通段階で価格がさらに上がっています。
備蓄米の放出や価格安定策の遅れがあります。政府は備蓄米を市場に放出していますが、供給不足感がすぐには解消されず、価格が下がるまでには時間がかかっています。
6,生産者の減少と高齢化スピードが加速
日本の米農家では、生産者の高齢化が急速に進んでいます。現役の米農家の平均年齢は年々上昇しており、特に中小規模の農家では若い後継者が極端に不足しているのが現状です。
2024年に廃業した米農家のうち、代表者が70代以上のケースが6割を超え、60代を含めると約8割に達しています。こうした高齢化の進行により、農業技術やノウハウの継承が難しくなり、新しい技術や省力化のためのツールの導入も遅れがちです。
■合鴨コシヒカリ 斎藤さん
▼ 商品のお取りよせはこちら
 山形つや姫特集 特別栽培のお米
山形つや姫特集 特別栽培のお米
つや姫の一番の特徴は、なんと言ってもその「美味しさ」です。際立つ「粒の大きさ」、「白い輝き」「旨さ」「香り」、「粘り」は、ごはんそのものがご馳走。
白ごはんで勝負できるお米を目的につくられました。つや姫の開発は、ごはんの旨みで勝負するために白いご飯が限りなく好きな人のためにと想いが込められています。
また、生産の方法は限定の田んぼと限定された生産者だけに許された厳しい認定制度の中で生産されています。「栽培適地」「生産者認定」「特別栽培」「品質基準」という4つの厳しい基準をすべてクリアした安心で美味しいお米だけが「つや姫」として流通できます。
(財)日本穀物検定協会の食味官能試験(実際に食べてみて、食味を判断する)において、外観については「艶がある」、「粒が揃っている」など、味については「甘みがある」、「うまみがある」などの評価が得られました。
その美味しさのルーツは明治時代に冷害の中でしっかり穂を着けた1本の稲から生まれた日本の美味しいお米のルーツといわれる「亀の尾」という品種に由来しています。