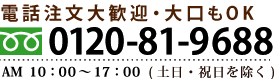さわす(柿の渋抜き)とは渋柿を甘くすることをいいます。これを一般に脱渋(脱渋)といいます。「さわす」という言葉の地域性は新潟県など一部の地域や庄内地方(山形県)で使われるローカルな言葉です。標準語では「柿を醂す(さわす)」と書かれ、辞書にも載っている言葉です。 &n...... 続きを読む
りんごを使った脱渋(エチレンによる脱渋) 1,柿とリンゴを準備します。渋柿5個に対し、りんご1個の割合で用意します。 2,密閉して保管します。渋柿とりんごをビニール袋に入れ、口をしっかりと閉じて密閉します。 3,熟成します。気温にもよりますが1週間ほど置くと...... 続きを読む
自宅での簡単な脱渋方法とは 渋柿の脱渋には、柿を焼酎などのアルコールに漬けてビニール袋で密閉する方法や、りんごと一緒に袋に入れて追熟させる方法や収穫後に皮をむいて吊るし乾燥させる方法(干し柿)もあります。また、特定の固形脱渋剤やドライアイスの炭酸を使う方法もあります な...... 続きを読む
また、柿の脱渋(しぶぬき)には大きく、炭酸ガス脱渋とアルコール脱渋があります。焼酎脱渋はアルコール脱渋のⅠ種です。炭酸ガス脱渋の味の評価については、アルコール脱渋に比べて風味やうま味がやや失われるという欠点がありますが反面、長所としては日持ちがやや長いとされています。 ...... 続きを読む
焼酎脱渋の美味しさの特徴とはコクのある甘みに加えて炭酸ガスを使った脱渋法に比べその味が濃く深みのある食味になるとされています。焼酎脱渋することでなめらかな食感、果肉がソフトな歯触りに変化する品種の渋柿もあります。特に庄内柿など「平核無(ひらたねなし)」という品種はそれにあた...... 続きを読む
柿の摂取量の目安は「1日およそ1個(約200g)」です。 ここまで紹介したように柿の食べすぎにはたしかに注意が必要ですが、適量を守って食べることでビタミンやミネラルを効率的に摂ることができます。 柿には魅力的な栄養成分がた...... 続きを読む
以下のような身体に対しての効果が期待できます。 免疫力の向上 柿には豊富なビタミンCが含まれています。ビタミンCは白血球の働きを助け、免疫力を高める効果があります。柿1個で1日に必要なビタミンCを摂取できます。 &n...... 続きを読む
柿の渋抜きにアルコールを使用する場合、一般的には以下の期間で渋が抜けます: 通常のアルコール(焼酎など):1週間程度 高アルコール度数のお酒(44%など):5日から7日程度 アルコール度数が高い専用の渋抜き酒:5日程度 ...... 続きを読む
庄内柿の渋抜きするメカニズムとその方法は次の通りです。 アルコール脱渋では、38%程度のアルコール溶液を柿1kg当たり10cc程度噴霧し、ビニール袋などで密閉することにより、1週間前後で渋が抜けま...... 続きを読む
和歌山県は「紀ノ川柿」という高級ブランド柿が有名。富有柿も高品質で知られています。 日本における柿の生産量上位3県とその生産量は次の通りです。 和歌山県: 約42,000トン(全国シェア19.4%) 奈良県: 約29,500トン(全国シェア...... 続きを読む
甘柿と渋柿の最大の違いは、含まれるタンニンの性質にあります。 甘柿: タンニンが不溶性で、口の中が溶けないため渋みを感じません。 渋柿::タンニンが水溶性で、口の中で溶けて渋みを感じます。 甘柿・渋柿の食べ方の...... 続きを読む
明治23年旧庄内藩の藩士、酒井調良氏が庄内柿の始まりと普及に大きく関わっています。珍しい種なしの柿を知人から譲り受けて、積極的に栽培を始めました酒井氏は庄内柿の普及に大きく貢献し、「庄内柿の父」と呼ばれるようになりました。この時期、庄内柿は「調良柿」とも呼ばれていました。 ...... 続きを読む
固めの状態が好きな場合は乾燥しないようにポリ袋に入れて冷蔵後の野菜室で保管して下さい。 熟してやわらかくなった柿はポリ袋に入れて冷蔵後の野菜室で保管し早めに食べるようにしましょう。 柿は、熟成を促進するエチレンガスを放出するので、他の果物や野菜と一緒に保存するとそれらの成熟を促してしまいます。冷蔵庫の野菜室で保存する場合は、必ず密封した状態で保管して下さい。...... 続きを読む