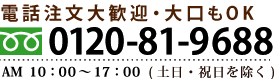さつまいも原産地はメキシコ周辺
サツマイモの原産地は、現在のメキシコ中央部からグアテマラ周辺の熱帯アメリカです。サツマイモはもともと北アメリカ南部、現在のメキシコ中部で生まれ、紀元前のうちにアンデス地方など、アメリカ大陸の文明全体に広まったとされます。紀元前800~1000年ごろには中央アンデス地方でも栽培されるようになり、ペルーの古代遺跡でサツマイモを描いた土器も発見されています。
アメリカ大陸が原産の野菜はサツマイモの他にもたくさんあります。トマト、トウモロコシ、ジャガイモなどの主要な野菜など食生活に無いと困るものばかり。さらにはトウガラシやタバコといった作物がアメリカ大陸原産の作物です。

メキシコのマヤ文明のピラミッドは、チチェン・イッツァ遺跡
さつまいもは暖かい東南アジアへ
大航海時代の15世紀の終わりに南米大陸の国家を征服したスペイン人がさつまいもをアメリカに持ち帰ったことで、ヨーロッパにもサツマイモが広まります。
ところが、比較的涼しい気候のヨーロッパ事態ではあまり栽培が広まりませんでした。もちろん、今でもサツマイモはヨーロッパでは普及していません。その代わりに、ヨーロッパ諸国の植民地、つまりアフリカ大陸やインド、東南アジアなどの地域でサツマイモの栽培が広まっていきました。
主に植民地だった地域の温暖なアフリカやインド、東南アジアなど暖かい地域に広まりました。そこから中国福建省には1584年に伝わり、中国の南方を経由して1605年頃、琉球(沖縄)に伝来しました。

琉球王国は中国と交易しさつまいもが伝来する
中国から琉球王国そして日本
1605年に琉球王国の使者が中国からサツマイモを持ち帰ったことで、日本の本州に先駆けて琉球全土で栽培が始まりました。 その後1609年に琉球王国は鹿児島の薩摩藩に征服され、この時にサツマイモの栽培が薩摩藩に伝わったというのがサツマイモ日本伝来の有力な説の一つです。
このようにして薩摩から全国に伝わったことから、サツマイモという名称がつきました。また、薩摩に伝わったのと同じころ、イギリス人のウィリアム=アダムスが途中寄港した琉球の那覇港でサツマイモを知り、それを平戸に持ち帰って栽培を始めたと言われています。今でも鹿児島県は日本のサツマイモ生産量で圧倒的な一位を誇っています。
江戸時代、さつまいもは中国から伝わったという意味で「唐いも(カライモ)」中国での名称と同じく「甘藷」という名前でも呼ばれていたと伝えられています。
日本への最初の伝来は、1597年に宮古島に入ったのが記録に残る最初とされ、まず琉球で栽培され始めました。その後、薩摩(現在の鹿児島県)へ伝わり、全国的に普及するようになりました。特に江戸時代の飢饉の際には救荒作物として注目され、日本全国に広がりました。

さつまいも村の村長の阿部さん
儀間真常が琉球王国で栽培の普及
儀間真常(ぎま しんじょう)に関する詳細な記録は、琉球の歴史書『琉球国由来記』(1713年成立)やその漢文校訂版『琉球国旧記』(1731年成立)、さらには正史にあたる『球陽』(1745年成立)に関連する記述があるとされています。
『球陽』は琉球王府の正史であり、これらの史料に基づいて儀間真常が中国から伝わったサツマイモの栽培普及に尽力し、琉球の食文化において重要な役割を果たしたことが伝わっています。
この頃の琉球の事情は頻繁にやってくる台風のため作物が育たない。琉球国として「慢性的な飢えをどう解消するか」これが当時最大の関心事でした。明国からサツマイモ栽培により飢饉が収まり、製糖技術によって産業が興てきます。これは琉球王国を支える変革となりました。
儀間真常は沖縄産業の父といわれ明国からサツマイモ栽培やサトウキビを原料にした製糖の技術を導入し、沖縄産業の礎を築き、食糧政策の面ではサツマイモの栽培を確立し普及に努めました。

青木昆陽はさつまいもの普及に努め救荒作物に
青木昆陽とサツマイモ
上記の他にもサツマイモが日本に伝播したルートは複数あったと考えられていますが、とにもかくにも江戸時代中期のうちにサツマイモは日本全国に伝えられました。そんなサツマイモの栽培を更に盛んにさせたのが青木昆陽(あおき こんよう)という人物でした。青木昆陽は享保の大飢饉に際して8代将軍徳川吉宗によって登用された人物です。
著作『蕃藷考』(1735)の中で飢饉のときの代用作物として栽培を奨励し、その結果サツマイモの栽培が急速に全国に広まりました。昆陽の施策によって、後に起こった天明の飢饉では多くの人が命を救われたと言われています。この功績によって青木昆陽は「甘藷先生」とも呼ばれています。

砂丘の砂の中の畑に美味しいサツマイモが育つ
享保の大飢饉とサツマイモ
享保の飢饉(きょうほうのききん)は、1732年(享保17年)に西日本を中心に発生した江戸時代の大飢饉です。死者は数千人規模に及び、都市部では米価高騰による初めての打ちこわし事件(高間騒動)も発生しました。
当時の食糧の中心であった米の生産量は大きく下落しました。この飢饉では少なくとも数万人、一説によれば100万人近い人々が命を落としたと伝えられています。この時に薩摩では餓死者がほとんどなかったのです。サツマイモがその飢饉から救ったのです。この事実が8代吉宗の食糧政策に影響し、青木昆陽がサツマイモを普及することに繋がります。

江戸期の飢饉を救った救荒作物さつまいも
サツマイモの力を知る吉宗
この飢饉の際に、サツマイモが栽培されていた薩摩地域では、餓死者がほとんど出なかったという情報が将軍・徳川吉宗のもとに伝わりました。他国にはさつまいもはなかった時代です。
青木昆陽の功績は大きいものがあります。吉宗は儒学者である青木昆陽(あおき こんよう)にサツマイモの栽培を命じました。昆陽は『蕃薯考』を著してサツマイモの特性と救荒作物としての重要性を説き、その栽培方法を確立して全国に広めました。
その結果、幕府の支援のもとサツマイモ栽培が拡大したことで、その後、天明の大飢饉(1782年〜1787年)など、飢饉が頻発する時代に多くの人々の命を救う重要な役割を果たしました。
https://youtu.be/_BDN5CF6_Yk?si=SWNT2mW2wQfv4Uo1