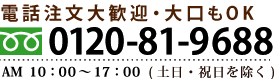写真は5月の月山、雪とブナ林
生産者の減少と高齢化の現状
日本のおコメ生産者人口は、長期的に減少傾向が続いています。1955年には農家人口が約3,635万人でしたが、その後一貫して減少し、2020年には約349万人まで落ち込みました。また、総農家数も1955年の約604万戸から2020年には約175万戸へと大幅に減少しています。
特に水稲(おコメ)農家に限ると、1970年には約466万戸あったものが、2020年には約70万戸と、50年間で7割減少しています。このように、おコメ生産者人口は急速に減少しており、同時に高齢化も進行しています。

春作業は、お天気に翻弄される。代搔き作業
コメの生産能力が低下し深刻な事態に
この背景には、農業従事者の高齢化や後継者不足、農業の収益性の低下などがあり、今後も減少傾向が続くと見込まれています。このまま高齢化が進行し続ければ、米の安定供給や日本の食料自給率の維持が困難になる恐れがあります。持続可能な農業を実現するためには、後継者の育成や農業経営の支援など、抜本的な改革が急務となっています。
温暖化によるとみられる被害には、お米の品質低下による被害、お米そのものの収穫量が低下する被害。これが重なり合って大きな収穫量の低下を招きます。近年の高温障害によるとみられる被害は深刻で、年々大きくなっていることを現場では実感しています。

丈夫な苗を作り、稲刈りから逆算で田植えする
極端な高温障害が頻発している
地球温暖化は、日本のお米作りに大きな影響を与えています。近年、気温の上昇や異常気象が頻発することで、お米の収穫量や品質にさまざまな課題が生じています。特に、稲の穂が出た後の登熟期間に高温が続くと、「白未熟粒」や「胴割粒」といった品質の低下が起こりやすくなります。さらに、極端な高温の年や一部地域では、収穫量自体が減少するケースも見られます。
その一つの大きな要因に「米の種子」の品質低下が考えられます。高温障害のもたらす継続した収穫量の低下には充実度の低い種子が原因しているとも考えられます。お米の種子を生産する各都道府県の種子生産地が高温障害受けて種子の品質が低下していると考えられます。種子まで高温障害の影響で深刻な事態になってるという指摘もあります。

すすむ高齢化が一段と米作りを難しくしている
自然災害による被害も頻発する
また、温暖化によって集中豪雨や台風の発生が増え、冠水や土壌流出、暴風による稲の倒伏などの被害も拡大しています。これにより、収穫量の減少や品質の低下が一層深刻化しています。加えて、温暖化の影響で害虫や病害の発生時期が早まり、被害が拡大する傾向も見られます。例えば、トビイロウンカや斑点米カメムシ類などの害虫被害が増加し、稲の「坪枯れ」や斑点米の発生が問題となっています。
地域によっては、温暖化により冷害が減少し、収量が増える可能性も指摘されていますが、全国的には高温障害や品質低下のリスクが高まっています。今後、気温がさらに上昇することが予測されており、お米作りへの影響が一層深刻になると考えられています。
こうした状況に対応するため、農業現場では高温に強い品種の開発や、栽培時期の調整、適切な水管理、害虫対策など、さまざまな工夫や技術開発が進められています。今後も行政や研究機関、農業団体が連携し、持続可能なお米作りのための適応策を強化していくことが求められています。

お米の粒が充実しない、実入りが少ない
米の高温障害のメカニズムとは
コメの高温障害は、主に登熟期(出穂から収穫まで)に気温が高くなることで発生し、米の品質や収量に大きな悪影響を及ぼします。メカニズムは以下の通りです。
まず、登熟初期に高温(特に昼温35℃、夜温30℃以上)が続くと、胚乳のでんぷん合成酵素の活性が著しく低下します。この酵素活性の低下は、常温に戻しても回復せず、胚乳のでんぷん合成機能そのものに障害が生じます。その結果、胚乳に十分なでんぷんが蓄積されず、白未熟粒や乳白米などの品質低下が発生します。
また、高温環境下では稲の呼吸量が増加し、日中に光合成で生産したでんぷんが夜間の呼吸で多く消費されてしまいます。そのため、穂に送り込まれる養分が減り、登熟歩合が低下します。加えて、水田の水温が30℃を超えると根の機能が低下し、養分や水分の吸収が困難になり、さらに障害が助長されます。
さらに、開花期に高温となると、受粉や受精がうまくいかず「不稔米」が増加し、登熟期の高温や乾燥によっては「胴割粒」も発生しやすくなります。このように、コメの高温障害は、酵素活性の低下によるでんぷん合成障害、呼吸量増加による養分不足、根の機能低下、受粉不良など、複数の生理的要因が複雑に絡み合って発生します。

粒が充実しないと米の重さが軽くなる
高温障害を予防する具体的な対策
コメ(稲)の高温障害を予防するには、以下のような多角的な対策が有効です。
高温耐性品種の導入
高温に強い品種、例として「にこまる」「笑みの絆」「つや姫」「雪若丸」を選ぶことで、登熟期の高温でも品質や収量を維持しやすくなります。
水管理の徹底
登熟期には間断かん水や湛水管理を行い、水田の水温を下げて根の活力を維持します。乾燥や強風時は湛水を保ち、出穂後30日以降に落水するなど、生育ステージに応じた水管理が重要です。
適切な施肥管理
出穂前30~50日にケイ酸カリなどの追肥を行い、登熟期の窒素不足を防ぐことで高温障害の軽減を図ります。
土作りと作土の深さ確保
堆肥を施し、作土深を20cm以上にして土壌環境を整えることで、稲の体力を高め高温耐性を向上させます。
高温期の水管理のポイントは
高温期の水管理のポイントは、稲の根の健全さと田んぼの水温コントロールを両立させることです。具体的には、以下の点が重要です。
深水管理と中干しの組み合わせ
高温期には水深20cm程度の深水管理を行い、田んぼの水温上昇を抑えます。ただし、根が弱らないように中干しも2回程度実施し、根に酸素を供給して稲の活力を維持します。
かけ流しによる水温低下
猛暑時には水深5cm程度でかけ流しを行い、田んぼの水温を下げて米の品質低下(シラタ発生など)を防ぎます。
水管理とタイミングが大切
朝から気温が高い日は、夜間や早朝に入水することで、用水温と水田水温の差を小さくし、水温の急上昇を防ぎます。
間断かんがい・走り水の活用
登熟期には間断かんがいや走り水を併用し、土壌表面のひび割れや過度な乾燥を避けます。
土壌や圃場の適切なメンテナンス
溝切りや田起こしを行い、排水性と保水性のバランスを整えることで、効率的な水管理が可能になります。圃場が平らなことが水管理を容易にします。稲刈後や、春作業の時期に田んぼを均平にする作業を行うことが大切。
これらの肥培管理を適切に行うことで、高温期でも稲の根の健全性と米の品質を守ることができます。
■お米の収穫作業、稲刈り