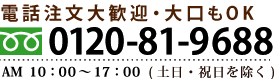お米作りする人がいなくなる
ここ数年の食用のお米の問題は深刻で、価格、品質、収穫量、生産力、生産体系、温暖化による気候変動、風水害など多くの問題を巻き込んで見直しが求められています。大きな問題としては、もちろん地球温暖化という、地球規模の問題そして、日本の農業が抱える問題、特に高齢化と、後継者不足という生産人口の急激な減少の問題です。
また、長年日本が続けてきた減反政策によって、おコメ作りへの将来不安から新規の就農者が激減しています。それと、お米の在庫の問題も大きく、財政支出を抑えるために在庫をできるだけ少なくしてきたので、少しのお米不足が、即、お米価格の高騰とつながってしまいます。

東北のお米は9月の夜温が低いことが品質につながる
お米の炭酸同化作用、光合成とは
炭酸同化作用とは、稲(お米の植物)が光のエネルギーを使い、空気中の二酸化炭素(CO₂)と水から有機物(主にブドウ糖)を合成する生理作用です。これは一般的に「光合成」と同義で使われます。
炭酸同化作用の仕組みは稲の葉に含まれる葉緑素が、太陽光のエネルギーを受け取ります。葉は空気中の二酸化炭素と、田んぼの水を取り込みます。光エネルギーを利用して、二酸化炭素と水からブドウ糖(有機化合物)を合成します。この過程で酸素が放出されます。
合成されたブドウ糖は穂に運ばれ、鎖状につながってデンプンとして蓄積され、これが最終的に「お米」となり実ります。

8月に開花受精し籾にでんぷんが蓄積する9月の夜温が大切
実りの秋の夜の気温が低いが理想
稲の生長やお米の収量は、この炭酸同化作用(光合成)がどれだけ活発に行われるかに大きく依存します。炭酸同化作用によって生産された有機物(ブドウ糖やデンプン)は、稲自身の成長だけでなく、稲籾の中にでんぷんとして蓄積され最終的には私たちが食べるお米のとなります。この時の夜の気温が低いことが重要。
炭酸同化作用を高めるための条件は十分な水分、葉緑素とタンパク質が豊富であること二酸化炭素が十分に供給されること。葉に十分な光が当たること、稲の葉は細長く、立ち上がるように配置されており、できるだけ多くの葉に光が当たるよう工夫されています。
また、田植えの際の稲の密度も、光合成効率を最大化するために調整されます。「炭酸同化作用」は「光合成」の別名です。特に学校教育では「炭酸同化」と呼ばれることもあります。
お米の炭酸同化作用とは、稲が太陽の光を利用して二酸化炭素と水からブドウ糖を作り出し、そのブドウ糖がデンプンとなってお米になる過程です。これは光合成そのものであり、お米の生産や品質の根幹をなす重要な生命活動です。

8月のお米の登熟期は夜温が低いことと、冷たい水が良い条件
お米の登熟と温度格差 日較差とは
お米(稲)の登熟期における「温度格差(昼夜の気温差)」は、登熟の進行や玄米の品質・収量に大きな影響を与えます。登熟期には昼夜の温度格差が大きいほど登熟が良好になり、最終的な収量が多くなることが現場でもよく知られています。最近の高温障害とは夜温が下がらないことに起因します。
日中の高温(25〜30℃程度)は光合成を活発にし、登熟を促進しますが、夜間の温度が高すぎると呼吸が旺盛になると蓄積する糖分の消耗が大きくなり、炭水化物の蓄積効率が下がります。逆に、夜間の温度が適度に低いと、呼吸によるロスが抑えられ、日中に作られた糖質がより多く玄米に蓄積されます。
イネは呼吸が旺盛になると自身の蓄積を減らして自身の体を守ろうとするからで、これはお米に限らず、植物全体に共通する原理です。ですから、果樹などは産地が内陸部に発達するのは、雨などが少ない盆地が多いのは温度格差も大きく美味しい果実が出来るのと同じ仕組みです。

庄内平野は最上川によって堆積した平野
日中の猛暑より高夜温の害が深刻に
高温や高夜温の影響は深刻です。登熟期に高夜温が続くと、粒重増加速度や玄米への乾物分配率が低下し、胚乳細胞の成長も抑制され、玄米1粒重や外観品質が低下します。
出穂後10日間の平均日最高気温が30℃以上、または出穂後20日間の平均気温が26℃以上になると、胴割米や白未熟米などの登熟障害が発生しやすくなります。こうなると、品質・収量への影響は大きくなります。
日本の主要品種では、登熟期間の平均気温が23℃を超えるとお米の重さが急激に減少しやすい傾向があります。低温でも登熟遅延や品質低下が起こりますが、高温・高夜温は特に粒の充実や外観品質、食味の低下を招きやすいです。
つまり、お米の登熟期には、昼夜の温度格差が大きい(昼は適度に高温・夜は涼しい)環境が理想的です。昼間の高温で光合成を促進しつつ、夜間の低温で呼吸ロスを抑えることで、炭水化物の蓄積効率が高まり、良質で充実した玄米が得られます。これが高収量、豊作につながります。
高温・高夜温が続くと登熟障害や品質低下が起こりやすく、適切な水管理や栽培管理で稲体の健全さを保つことが重要ですが、冷品質と不作に繋がっていきます。

8月上旬に庄内では稲の花が開花する
高夜温が登熟に与える影響は甚大
高夜温(夜間の気温が高い状態)は、お米の登熟にさまざまな悪影響を及ぼします。
■玄米1粒重の低下(お米が軽くなる)
登熟期に夜温が高いと、玄米1粒重が明らかに低下します。これは昼間の高温よりも夜間の高温のほうが粒重への悪影響が大きいことが実験で示されています。
■呼吸量の増大で消耗
夜間の温度が高いと稲体の呼吸量が増え、日中に光合成で作られた炭水化物が消費されやすくなり、穂への転流量が減少します。
このように、高夜温は、お米の登熟において玄米1粒重や外観品質の低下、粒の充実不良、炭水化物の消耗増加など、さまざまな悪影響を及ぼします。
特に夜間の高温は昼間の高温よりも登熟障害の要因として重要であり、良質なお米を収穫するためには登熟期の夜温管理が極めて重要です。

稲の穂が出る8月から9月はお米の美味しさ収量の決まる頃
お米が登熟するために必要な条件
登熟(とうじゅく)とは、稲の穂が出て開花・受粉した後、モミ、種子(お米)が発育・肥大し、デンプンが蓄積されていく過程を指します。この登熟を順調に進めて良質なお米を収穫するためには、以下のような条件が重要です。
適切な気温
お米の実りの秋は登熟期間(出穂後40~50日間)には、平均気温22℃前後が理想とされます。夜温が涼しいほど稔りは理想に近くなります。とても重要な収穫量に影響する要素です。登熟期に高温(最高気温32℃、平均気温27~28℃、最低気温24℃以上)が続くと、白未熟粒や胴割粒など品質低下の原因となります。
十分な日照・光合成
登熟期に晴天が続くことで光合成が活発になり、デンプンの蓄積が進みます。日照不足や曇天が続くと、登熟が不良になりやすい。
昼夜の寒暖差
昼間は暑く、夜間は涼しいという寒暖差のある天候が理想的です。夜温が高いと稲の呼吸が盛んになり、昼間に作られたブドウ糖が消費されてしまい、登熟が悪くなります。
適切な水管理
登熟期は田面が乾かないように水を切らさないことが重要です。出穂期後30日間は落水を避け、間断かんがい(適度に水を入れる管理)を行います。
このように、お米が登熟するためには、「適温・十分な日照・寒暖差のある気候・適切な水と肥料管理・根の活力・病害虫防除」など、複数の条件がバランス良く整うことや、特に登熟期は夜温が低くなることが最も重要です。特に登熟期の気温と水管理は、収量と品質に大きく影響します。豊作を左右する絶対状意見といえるのです。
■庄内平野のコメ作りから代掻き