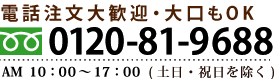りんごコンポートにして冷凍 りんごの冷凍保存は1個のままダイレクトに冷凍するより出来ればひと手間かけ調理して冷凍保存したいものです。そして小分けにして保存することで次に食べるときの利用方法が簡単便利になります。 コンポートにすることでおしゃれにスイーツ、デザートなどバリエーションが広がり、その時々の調理の手間を省けることにもつながります。ここは大いに研究してみる必要がありそうですね。 ...... 続きを読む
くだもの歳時記
上の写真は「こうとく」のこれ以上ない蜜入り(左)とまずますの蜜入り(右)です。 蜜入りリンゴ選びのコツとは りんごの美味しさの基準になっている「蜜入り」のりんご。たくさんのりんごの中から「蜜入りりんご」を見分けるコツがわかれば、嬉しいですよね。今回は、りんごのプロが「蜜入りリンゴの見分け方 選び方」をお教えします。 ただし「りんごの蜜」はすべての品種に発生するわけではありません。品種によって大き...... 続きを読む
食品ロス問題は身近にある 親類や知人、ご近所から貰ったり、旬の時期の安いときにネットショップで訳ありりんごを箱買いしたりするりんごですが、食べ忘れや気がつくと意外に傷んでいたり、もったいない思いをしたことはないでしょうか。旅行に行ったりするとてき面に食品のこと忘れます。 そこで、長期間保存が可能になる方法と、その冷凍したりんごを活用した保存方法と活用方法を考えてみたいと思います。 冷凍保存すると...... 続きを読む
りんごの変色防止の方法とは 「朝の果物は金」とよく言われますが「朝のりんごも金」といえるでしょう。旬のりんごにはカルシウム・カリウム・食物繊維・鉄分・ビタミンCを豊富に含んでおり、体にいい食べ物といえるくだものの王者です。 ここでは、この身体にいいとされるリンゴを沢山食べてもらうための知恵を皆さんと分かち合いたいと思います。そもそも、どうしてりんごは変色してしまうのでしょうか。りんごには、ポリフェノールが含まれています。 ...... 続きを読む
手がすべるけどクシ切りに 通常の食べ方としてはラフランスは、クシ切りです。皮をむかずに4等分に切ります。真ん中の軸の部分をりんごのように切ります。8等分に切ったりしてもいいです。お好みの大きさに切って最後に皮を薄くむいて、お召し上がり下さい。 完熟になったラフランスは冷蔵庫に冷やしていただきます。皮をむいて芯を取りだしてリンゴのように皮をむいてクシ形に切って食べるのもいいのですが、完熟したラフランスは果汁が滴り手がぐちゃぐちゃに汚れ...... 続きを読む
りんごの自然のろう物質の分泌 「スーパーで買ったラップ包装したりんご(サンつがる)を 数日後に食べようとしたら、表皮がベトベトしていました。ワックスを使っているのではないでしょうか?」 このようなお問い合わせが時々あるようです。 表面がピカピカ光って、手で触れると油のようにベタつく果実があります。品種によって表面がベタつきやすくなったり、ならなかったりします。 ...... 続きを読む
りんごの皮むきの優れもの おいしいのは分かっているけれど、むいたり切ったりするのが意外と面倒くさいという意見が多い。そんな面倒なフルーツのための専用カッターがあります。今回はあっという間に切れて、使うのが楽しくなるフルーツカッターの中からりんごにカッターに注目し徹底検証してみたいと思います。 この道のプロといわれる合羽橋の老舗料理道具店の6代目、料理道具研究家、飯田結太氏がイマドキの料理道具を徹底研究しているとお聴きし「フルーツカッター」に...... 続きを読む
啓翁桜が冬に満開する仕組み 「啓翁桜」は、1930年に福岡県久留米市山本の良永啓太郎氏が中国系のミザクラを台木にしてヒガンザクラを接いだところ、穂木として使ったヒガンザクラからその枝変わりとして出来たものといわれています。 お正月にも満開の桜が楽しめる、啓翁桜の促成栽培が始まったのは、昭和40年代後半のことです。山形県は全国的にもこの栽培では早くスタートし、啓翁桜の栽培が山形県の気候にマッチしたことから今では日本一の産地になって...... 続きを読む
ラフランス不細工の代名詞 これからお話しするのは、まさにラフランスが辿ってきた「シンデレラストーリー」と呼ぶにふさわしいお話です。 山形弁で「みだぐなす」という言葉があります。直訳すると「見ためよくなし」といい、訛って「なす」とは「なし」「梨」でもあり、つまり「みだぐなす=みばえが悪くかっこ悪い梨」という見下した卑下する意味が込められた言葉です。 ラフランスが脚光を浴びる以前...... 続きを読む
ラフランス完熟が見えない 当初は高価な果物としてわずかに出回っていましたが、グルメブームの到来で、広く一般的に入手できるようになったのは最近のことです。ラフランスの生食が一般化するのにいちばんの問題は食べ頃が判りずらいことでした。そして、この問題に関しての具体的な対策をどうするかという課題の克服にあったのです。その結果山形では、予冷というルールを一般化して食べ頃となる完熟期を明確化することになったのです。 ラフランスが流...... 続きを読む
ラフランス食べ頃は完熟のとき 「ラフランス」は食べ頃になっても果実の色が黄色に変色しない場合が多いので、プロでないと食べ頃の判断が難しい果物です。しかし、そのプロの使っているコツさえつかめば簡単に食べ頃がわかります。 ラフランスの食べ頃は完熟のときが最高の食べ頃といえます。またラフランスは食べ頃になるまで常温で保管して下さい。 食べ頃をむかえた「ラ・フランス」は濃厚で芳醇な香りととろけるようななめらかな舌触りで「西洋な...... 続きを読む
リンゴ保存で大事なのは水分 りんごは乾燥に弱いくだものです。水分が失われると美味しさも失われて食味が格段に落ちてしまいます。保存方法で大切なのは温度管理と水分の管理です。水分を保つことでおいしさが持続できます。 温度は通常は常温でいいのですが、暖房のきいた部屋は温度が高く乾燥もしていますから避けた方がいいでしょう。短期間の保管でしたら冷暗所もしくは冷蔵庫の野菜室にいれてください。 リンゴ...... 続きを読む
りんご皮むきは面倒だから りんごは皮をむいてくれたら食べるという人が圧倒的に多いことには頷けるところがあります。ちょっと甘えたお話しになりますがこれが本音でしょう。 さて、りんごを食べるときのキーポイントは「剥く」です。よく「剥いてくれたら食べるのに」という方が多くいるようです。自分で剥くのは嫌だし、めんどうくさいからですからね。 この面倒くさくて煩わしいコトを「楽しむ」に変えたらりんごも剥ける...... 続きを読む
無袋ふじは朝日町から全国区に ここ山形県朝日町は「ふじ」の無袋栽培を作り上げた発祥の産地として、そしてまた絶品の袋を架けない無袋栽培でつくられるサンふじの生産地として全国に知られています。「サンふじ」と呼ばれる無袋ふじ発祥の地 山形県朝日町は雪国山形県の中でも豪雪地帯です。 果実に袋をかけずに栽培される無袋栽培の朝日町のふじは、太陽の光をふんだんに 受けて育ちます。果肉の中には、完熟の証であるアメ色の蜜がたっ ぷり、さわ...... 続きを読む
柿の選び方 美味しい柿とは 秋になると庄内地方のあちらこちらの家で色付き始める柿の実。甘く柔らかく、歯ごたえもしっかりした柿、子供からお年寄りまでみんなが大好きな『庄内柿』です。庄内を代表する秋の果実『庄内柿』は、果実が甘く、適度の歯ごたえ、種がないのが特徴です。種なし柿、正式には『平核無柿(ひらたねなしかき 平らで種の無い柿、核とは種のこと)』と言います。 果肉が厚く色周りが良いものを選ぶといいでし...... 続きを読む
ラフランス選びは難しくない ラフランスは甘味の中にほんのり酸味があり、果汁たっぷりの果肉は濃厚な香り、にとろけるような食感、まろやかな口当たりで西洋なしの中でも高い評価を得ています。しかし、課題として熟しても果皮の色はあまり変わらず、食べ頃がわかりづらいという問題があります。 このように、食べ頃がが難しいゆえに完熟になると独特の香りが漂い軸の周りの果肉は弾力をおびて、果汁たっぷりのクリーミーな果肉を楽しむことが出来るので...... 続きを読む
フランスでは知らていない品種 ラフランスはフランスが原産で1864年に発見された品種です。甘味の中にほんのり酸味があり濃厚な味を楽しめます。果汁たっぷりの果肉はとろけるようなまろやかな口当たりで西洋なしの中でも一番の人気です。 日本ではようやく洋なしの品種として知られ始めていますが、本家本元、原産地のフランスでは絶滅の危機にあるというマイナーな存在と聞き及びます。 果実の平均サイズは200~250gくらいで出荷されるの...... 続きを読む
生食用の生プルーンの食べ方 プルーンとは西洋スモモのことを指します。日本すももに比べると酸味はさほど強くはありませんが、完熟にしないと美味しくありません。加工したドライフルーツや煮詰めて瓶詰のプルーンも「プルーン」と同じように呼ぶのでここでは間違わないよう「生プルーン」と言うようにします。 ですから加工されたプルーンとは別に美味しい果物としてのプルーンを皆様にお試しいただきたいので「生プルーン」と呼んで生食用を楽しんでい...... 続きを読む
白桃の旬は7月から10月まで 山形県でつくられるももの品種は、実の肉質が緻密な「あかつき」、大玉の「川中島白桃」、晩生種の「ゆうぞら」ほか。特に生食用の50%を占めるのが川中島白桃で、上品な香りに加えて日持ちも良く、質と量ともにトップにランク。8月下旬から9月上旬まで出荷されます。 白桃は早い順に、7月下旬のあまとう、あかつき、川中島白桃、9月だて白桃、10月上旬の夢かおりと続きます。 ところで、「ももの実」の表面...... 続きを読む
女性育種家 森屋初が育成 だだちゃ豆の下地は江戸期にあったとしても現在に残る正式な由来としてはより現在のものに近い形になったのは、具体的に「だだちゃ豆」は明治の後期に誕生したとされる記述もあります。 当時の大泉村白山に帰農した士族、森屋藤十郎の娘初が、隣村の寺田から貰い受けた早生種の茶豆の種を畑に植えたところ、なかに晩生で味の良い豆があったため、その種を大切に保存して自分の畑で増やしていき、現在のだだ...... 続きを読む